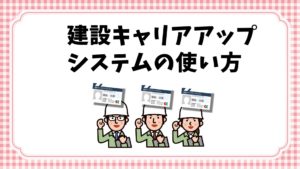建設業許可の「建築工事業」とは?
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、「建築工事」で建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「建築工事業」とは、どういう工事?
建設工事の内容を定める告示には、以下のように記載されています。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
「建築工事業」は、総合的な企画や指導、調整のもと、建築物を作る工事です。
一式工事は専門工事と異なり、総合的な企画や指導、調整のもと工事を行います。
建築一式工事の許可を持っていても、建築系の工事がすべて可能というわけではありません。
専門工事だけを行う場合、原則として専門工事の許可を受ける必要があります。
一般的には、建築確認を必要とする新築工事や増改築、大規模改修工事などが、建築一式工事に該当します。
建築物を下請専門工事業者を使って完成させていく業種になります。
2.「建築工事業」と似た工事は?
建設業許可事務ガイドラインに、区分の考え方が記載されています。
- 「避難階段」の切り分け
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
3.「建築工事業」の専任技術者になるには?
専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
必要とする国家資格や指定学科は、以下のページにてまとめていますので参考にしてください。