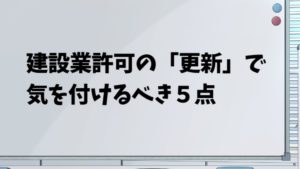建設業法の「工事の丸投げ」とは
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
建設業法では、一括下請負(工事の丸投げ)は原則禁止されています。
元請も下請も禁止されており、知らず知らずのうちに違反とならないように、注意する必要があります。
この記事では、建設業に携わる方に向けて説明しています。
1.一括下請負(工事の丸投げ)とは
一括下請負(工事の丸投げ)は、元請業者や下請業者はもちろん、1次下請業者、2次下請業者、それ以下の下請業者間でも原則禁止です。
違反した建設業者は、行動の態様、情状等を勘案し、監督処分(営業停止)を受けることになります。
親会社と子会社の間であっても、処分対象になります。
元請負人が下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負(工事の丸投げ)に該当します。
一括下請負(工事の丸投げ)に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事1件ごとに行います。
「実質的に関与」とは、下表の事項を行う事をいいます。
| 元請が果たすべき役割 | 下請が果たすべき役割 | |
|---|---|---|
| 施工計画の作成 | ○請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成 ○下請負人の作成した施工要領書等の確認 ○設計変更等に応じた施工計画書等の修正 | ○請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成 ○下請負人が作成した施工要領書等の確認 ○元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正 |
| 工程管理 | ○請け負った建設工事全体の進捗確認 ○下請負人間の工程調整 | ○請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認 |
| 品質管理 | ○請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、必要に応じた立会確認 | ○請け負った範囲の建設工事に関する立会確認(原則) ○元請負人への施工報告 |
| 安全管理 | ○安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置 | ○協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置 |
| 技術的指導 | ○請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 ○現場作業に係る実地の総括的技術指導 | ○請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守 ○現場作業に係る実地の技術指導※ |
| その他 | ○発注者等との協議・調整 ○下請負人からの協議事項への判断・対応 ○請け負った建設工事全体のコスト管理 ○近隣住民への説明 | ○元請負人との協議※ ○下請負人からの協議事項への判断・対応※ ○元請負人等の判断を踏まえた現場調整 ○請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理 ○施工確保のための下請負人調整 |
| ⇒ 元請は、以上の事項を全て行うことが求められる | ⇒ 下請は、以上の事項を主として行うことが求められる (注)※は、下請が、自ら請けた工事と同一の種類の工事について、単一の建設企業と更に下請契約を締結する場合に必須とする事項 |
以下のように部分的に請け負わせる場合でも、工事の丸投げの対象になります。
- 建築一式工事を請け負った元請業者が、自らは内装仕上工事のみを行い、その他すべての工事を下請業者に請け負わせるケース
- 外壁塗装工事を請け負った元請業者が、自らは足場工事のみを行い、塗装工事を下請業者に請け負わせるケース
- 戸建分譲住宅5戸の新築工事を請け負った元請業者が、そのうちの1戸を下請業者に請け負わせるケース
一括下請負(工事の丸投げ)を禁止しているのは、以下の理由のためです。
- 発注者の信頼を裏切ることになるため
発注者は建設業者の施工実績、施工能力、社会的信用等、評価を鑑みて信頼して契約をしています。 - 建設業全体への悪影響
工事の責任が曖昧になり、手抜工事が増え労働条件の悪化につながります。
また施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招きかねません。
建設業者は請け負った建設工事の完成について、誠実に履行しなければなりません。
2.一括下請負(工事の丸投げ)の例外規定
原則は一括下請負(工事の丸投げ)は禁止ですが、一定の場合だけ例外的に丸投げが出来る場合があります。
以下のすべてを満たした場合は、合法的に丸投げすることが出来ます。
- 民間工事であること
- 共同住宅を新築する工事以外
- 元請が発注者に、あらかじめ一括下請負することを書面で承諾を得ていること
重要なのが、「元請が発注者」にというところです。
下請が発注者に、承諾をもらっても要件を満たしたことにはなりません。
もう一つのポイントが、「あらかじめ書面で承諾」です。
工事の途中に丸投げしようと、発注者に話に行っても合法になりません。
また合法的に丸投げすることになったとしても、主任技術者や監理技術者は配置する必要があります。
もし一括下請負(工事の丸投げ)を違法に行ってしまったら、罰則が規定されています。
「丸投げした元請」も「丸投げされた下請」も、処分を受けることになっています。
下請業者は、「一括下請負(工事の丸投げ)をされてるのかどうか分かりにくい場合もあると思います。
下請業者としても、元請業者の管理体制に気を配ることが大事です。
一括下請負(工事の丸投げ)は、発注者の信頼を裏切る行為であり、重い処分を受けないように気を付けなければなりません。