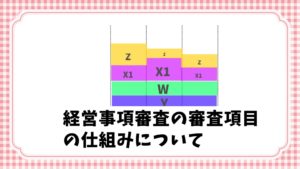建設業許可は必要?メリットとデメリット
軽く、Youtubeでも動画をアップしています。
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
元請さんから、「建設業許可を取得するように」と言われておられませんか?
この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて解説しています。
1.建設業許可が必要ではないケースとは?
建設業許可は、必ずしも必要とはしない場合もあります。
建設業許可を受けなくても施工できる工事は、以下のとおりです。
- 自ら使用する建設物を、自分で工事をする場合
- 宅建業者が、建売住宅を自社で工事をする場合
- 軽微な工事の場合
軽微な工事というのは、建設工事請負代金が1件あたり税込500万円未満の工事のことを言います。
ただし建築一式工事に限り、税込1500万円未満の工事又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事になります。
注意すべき点として、以下の2点あります。
契約書が複数に分かれていても、発注者、工事現場、完成すべき物が同一である場合は1件の工事です。
注文者が材料を提供する場合は、材料費(市場価格)と運送費を請負代金に足します。
上記の建設業許可が不要なケースを除く、すべての建設工事では建設業許可が必要となります。
建設業法では、許可を得ていない下請業者と、許可が必要な請負締結をした場合、発注者である建設業者も罰則が科されます。
そのためゼネコンなどの大手建設業者は、軽微な工事のみを下請発注するときでも、許可業者しか参入させない傾向があります。
2.建設業許可のメリットとデメリット
建設業許可を取得した場合、様々なメリットがありますが、多少のデメリットも生じます。
建設業許可を取得することによる主なメリットとして、次の4点があげられます。
- 大規模な建設工事を請負うことができる。
建設工事を取得すれば、請負金額の制限なく建設工事を受注・施工することができるようになります。
受注の機会を逃がすことがなくなり、売上増加に繋がります。 - 対外的な信用度が上がる。
建設業許可を取得するということは、厳しい要件をクリアしたことになり、発注者や官公庁などへ対外的にアピールすることができます。
金融機関や保証協会からの信用も得やすくなり、融資や資金調達を行う際に有利になります。 - 下請工事を受注しやすくなる。
公共工事では、許可業者を下請業者や孫請業者として請け負わせるように国土交通省が指導しています。
そのため元請業者が下請業者に発注する際には、建設業許可を受けていることが1つの判断材料となっています。 - 公共工事を受注することができるようになる。
公共工事を受注するためには、建設業許可を受けた後に経営事項審査を受けてから入札参加資格申請を行うという手続きになります。
そのため建設業許可を取得しなければ、公共工事に入札することができません。
建設業許可を取得するには生じるデメリットは、以下のとおりです。
- 申請手数料がかかる。
知事の新規申請は90,000円。大臣は新規申請は150,000円。
建設業の更新や業種追加する場合には、50,000円がかかります。 - 一定の重要な事項に変更が生じた場合は、変更届をする義務がある。
変更事項により、変更から14日以内又は30日以内に行う必要があります。 - 1事業年度毎に、決算変更届(決算報告)を行う必要がある。
決算から4か月以内に行う必要があります。 - 許可業者になると、守らないといけないルールがある。
現場に必ず資格者か、10年以上の実務経験がある配置技術者を置く必要があります。 - 申請書類の閲覧書類、決算変更届などを、誰でも閲覧することができるようになる。
発注者となる者を保護するための制度ですので、閲覧されるのを拒むことはできません。
事業者の情報を外部に公開されるので、営業電話も増えてしまいます。
3.気を付けるべき点
建設業許可が必要なのは、請負契約時のときです。
建設工事の施工前に、建設業許可を取ればOKというわけではありません。
許可を持っていないのに、500万円以上の建設工事の依頼があったら、どうすべきでしょうか?
「お断りをする」か、「許可を持っている建設業者を紹介する」しかありません。
建設業というのは金額も大きくなるので、凄く責任のある仕事です。
そのため、ある程度の信用力のある事業者に仕事をしてほしいという要請から、建設業許可という制度ができています。